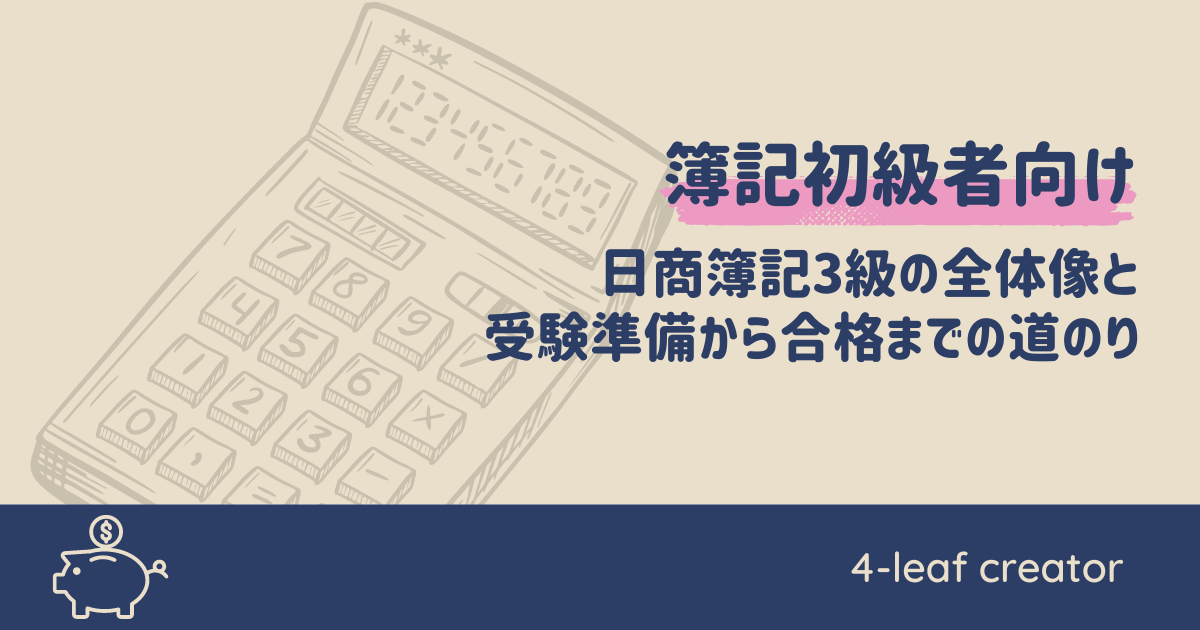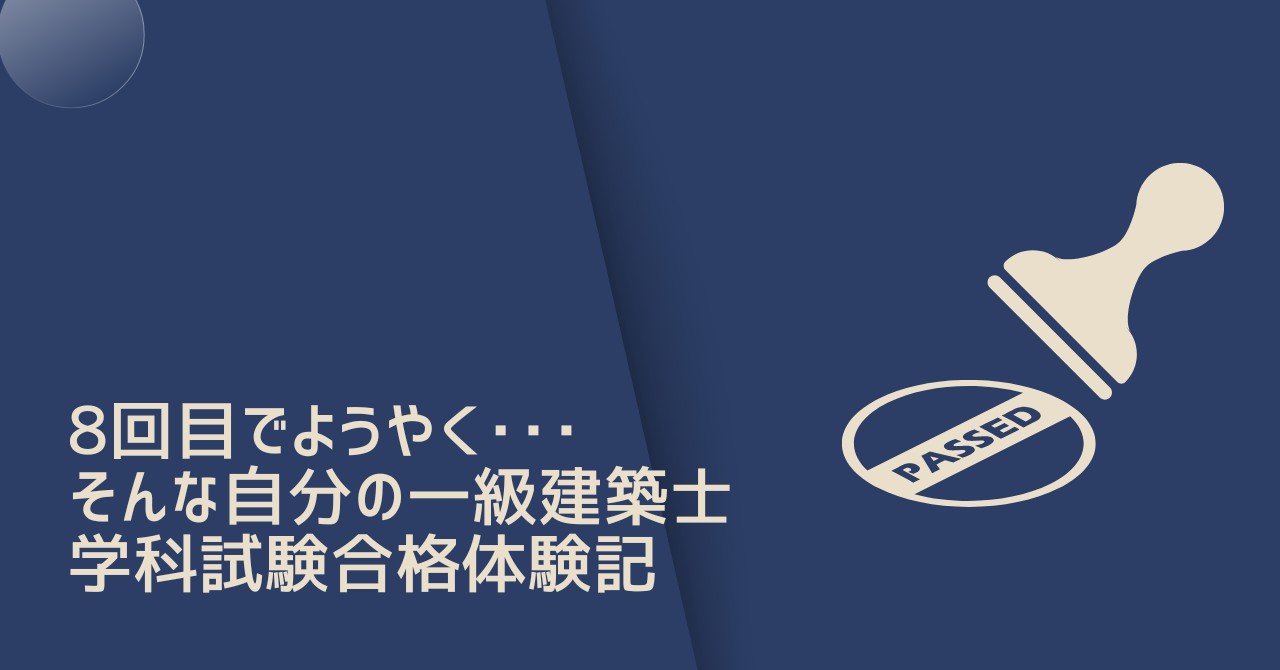少し時間はかかりましたが、簿記知識ゼロの状態から勉強を始め、日商簿記検定3級(第163回統一試験)に合格することができました。
「合格」という評価がもらえたのがとてつもなく久しぶりだったこともあって、うれしくて仕方がない。
まだうれしくて気分が高揚しているうちに日商簿記3級試験の概要や合格のためにやってきたこと、受験してみた感想などいろいろとまとめてみます。
なお、この記事を公開した時点で、合格は受験番号で確認できていますが、何点取って合格できたかがわかっていません。
成績がわかり次第追記していきます。
そもそも簿記って何?
企業規模の大小や業種、業態を問わずに、日々の経営活動を記録・計算・整理して、
日本商工会議所Webサイトより引用
経営成績と財政状態を明らかにする技能です。
「会社の中で取引されるお金やモノの流れを帳簿に記録すること」
引用文を簡単にするとこんなところでしょうか。
ちゃんと記録しておかないといつ何を取引したのか忘れてしまうし、会社の経営状況も今どうなっているのか把握することができません。
また、銀行からお金を借りるとき、自社の経営状況を見せなければいけないと思うのですが、こういう時にも取引の流れを記録した資料がないと銀行側としてはお金を貸しても良いのかどうか判断ができません。
自社の状況を知るためにも、対外的に自社の内容を伝えるためにもこのような記録は必要になってきます。
この記録を作る作業が【簿記】です。
この記録ですが、各会社それぞれが独自の作り方をしていたら記録の見方が各社それぞれのものになってしまい見にくいし、会社同士を比較することができません。
なので、この記録の仕方にはルールが決められています。
そのルールがわかっているかを証明するのが【簿記検定】になります。
簿記を勉強するメリットとは
通常会社では経理部がこの仕事を担当するので、経理部の人だけに必要な勉強なんじゃないかと思われがちですが、そんなことはありません。
「簿記の知識があるとこんなメリットがあるよ!」
というのが簿記を扱うWebサイトやブログ等で上がっています。
例えば、転職や就職に有利だとか、独立起業したときに役立つとか。いろいろなメリットがある中で、自分が一番のメリットだと思っているのがこれです。
会社の経営状況がわかる
上で書いた会社の中で取引されるお金やモノを記録した帳簿は「財務諸表」と呼ばれています。
簿記の知識があると、財務諸表を見て会社の経営状況を把握することができます。
これができると、今自分が勤めている会社の経営状況がわかるわけです。
会社の強みが弱みがわかってそれを経営に生かすことができます。
また、会社の経営状況が悪いとわかれば、いち早く転職の準備に取りかかるなんて事もできそうです。
最近株式に投資する人も増えてきていますが自分の会社の経営状況だけでなく、他の会社の経営状況も把握ができるので投資先を判断するにも役立ちます。
財務諸表の数字が読めるというのは、会計の目線からもモノを考えることができるという点でとても強力な武器になるのでは?と思ったのが簿記の勉強を始めた理由のひとつです。
正直なところ、まだ3級を取ったばかりなので財務諸表を見て会社の経営状況がわかるようになったわけではないですが、これからも簿記の勉強を続けていって最終的には財務諸表が読めるようになりたいです。
日商簿記検定とは
簿記検定はいくつかの試験団体があってそれぞれに検定試験を行っているようですが、この記事で紹介するのは日本商工会議所が行っている日商簿記検定(3級)です。
社会人が受ける簿記検定は日商簿記検定になるのかなと思います。
1級から3級まで設定されていて多くの人が2級まで取得されているようです。
ちなみに1級は合格率10%前後の相当難しい試験になっています。
合格すると税理士試験の受験資格も得られるようなレベルの高い試験です。
受験資格等がないので誰でも受験が可能です。
3級→2級→1級とステップアップして行く人が多いとは思いますが、いきなり1級を受験するとか、2級を受験すると言ったこともできます。
自分は全く簿記の知識が無いところからスタートしたので3級から始めました。
3級は簿記のルールというか原則を勉強するレベルなので簿記初心者はここから始めた方が絶対良いです。
なので、ここからは簿記3級試験についてまとめていきます。
日商簿記3級試験について
試験の形式について
統一試験
統一試験は、指定の会場で実施される筆記試験です。
年に3回実施されています。(2月、6月、11月)
合格発表は受験日から2~3週間後となっています。
※東京商工会議所だけの話ですが2023年度試験から簿記検定2,3級の統一試験(個人申込)が廃止となります。
団体試験は継続するようです。
https://kentei.tokyo-cci.or.jp/news/30.html
東京23区内での受験では個人申込での統一試験はなくなりますがその他の地域では今までと変わらず統一試験が実施されます。
ネット試験
ネット試験は、全国各地のテストセンターにてインターネット上で行われる試験です。
会場によって試験実施日が違うようですが、受験日や場所を自由に選ぶことができます。
また、受験結果がその場でわかるのも特徴です。
インターネット上での試験になるので問題用紙にメモを書くことができません。
試験前に筆記用具と紙をくれるのでそれにメモをしながら回答していきます。
ネット試験に対応した教材も数多く発売されているのでネット試験を受ける前に一度回答の流れを経験しておいた方がいいと思います。
試験時間と合格基準点
試験時間は60分です。
100点満点中70点以上で合格。(統一試験、ネット試験共通)
試験レベル
業種・職種にかかわらずビジネスパーソンが身に付けておくべき「必須の基本知識」として、
日本商工会議所Webサイトより引用
多くの企業から評価される資格。 基本的な商業簿記を修得し、
小規模企業における企業活動や会計実務を踏まえ、
経理関連書類の適切な処理を行うために求められるレベル。
3級で勉強することは簿記の基礎になる部分です。
簿記に関していろいろな知識を載せていくための土台になる部分という位置づけになっています。
合格率について
試験元のデータを見ると合格率は40~50%となっています。
ただ、統一試験では合格率が試験回によって浮き沈みが激しく、合格率が20%台の時が何度か見受けられるので、運悪く難しい回に当たってしまうと大変かもしれません。
一方、ネット試験の方は、合格率の浮き沈みがほとんど無く、安定しているようです。
合格率のことだけ考えると、ネット試験を受験した方が安心かもしれません。
下記に試験元が発表している受験者データへのリンクを貼っておくので詳しい情報はこちらをご参照ください。
その他
簿記3級統一試験は現在午前9時から始まる試験と午前11時から始まる試験があって受験申し込みの際にどちらで受験するかを選択することになります。
両方受験することはできません。
また、9時から始まる試験と11時から始まる試験は出題される問題が違うそうです。
ですので、どちらが簡単でどちらかが難しいといったような難易度のズレが少なからず発生するようです。
さらに、この試験はひたすら数字を計算していく必要があるので、電卓の使用が認められています。
試験を時間内に終わらせるためには計算スピードも上げる必要があるので、
受験準備のポイント
学習方法:独学か、通信教育か
受験前にいろいろ調べてみましたが、簿記3級試験を受験する人は独学か通信教育のどちらかで勉強している人がほとんどで、個人的な印象だと独学で勉強する人が圧倒的に多い印象を受けました。
ちなみに自分は通信教育を選択しました。
教材や参考書の選び方:多くの合格者が使用した教材を選ぶ
書籍
独学で勉強されて合格している方がブログやYouTubeで発信されている情報を見ていると下記の書籍を使っている人が多かったです。
通信講座
通信教育で勉強する人は下記の教材を使う人が多いようです。
ちなみに自分はスタディング簿記3級講座を使用しました。
統一試験が終わるとキャンペーン価格を打ち出してくる資格学校が多いので、もし通信講座を申込むとしたらこのタイミングがおすすめです。
YouTube動画等の無料講義
最近はYouTube等で有料級の講義を無料で視聴できるサービスが出ています。
こちらを使うのもおすすめです。
ここであげた教材は多くの合格者が使用していた教材です。
簿記はたくさんの教材が出ているので何を選んで良いかわからなくなってしまうかもしれませんが、この中から選んでもらえればどれを選んでも合格に必要な知識は身につきます。
また、教材は年に1回その時の法令に合わせて改訂が行われているようです。
教材を手に入れる前に、受験する年度の試験に対応しているものかを確認してください。
試験対策のポイント
試験対策その1:第1問と第3問で満点を狙う
簿記3級は以下のような問題が3問出題されます。
第1問:仕訳 15題(45点)
第2問:勘定記入、補助簿作成等 2題(20点)
第3問:精算書、財務諸表等作成 1題(35点)
※括弧内の点数は試験の配点
「第1問と第3問で満点を狙って第2問は部分点を拾う」
これが必勝パターンです。
なので、試験では第1問→第3問→第2問の順で解きました。
どの問題をやるにもしても必ず仕訳がついて回るので、仕訳が正確にできるように練習しておく必要があります。
仕訳の勉強をしながら、第3問対策をやって、第3問に慣れてきたところで第2問対策をやりました。
試験対策その2:ひとつの教材をひたすら反復演習する
自分はスタディング簿記3級講座を使って、教材の問題をひたすら反復演習しました。
スタディングを使った基本的な勉強の流れはこれだけ。
講義のあとに解いた演習問題はAI問題復習というシステムに組み込まれます。
このAI問題復習というのはその日にやった方がいい演習問題を勝手に出題してくれる機能です。
この機能に従って出題されるがままに問題を解きました。このシステムに乗っているだけで自然と反復演習できるという優れものです。
間違った問題は頻繁に出題されるので苦手な問題は何度解いたかわからないくらい解いたと思います。
演習問題をある程度やってから「実践力UPテスト」「検定対策模試」という実際の試験で出題される形式の問題演習に進みます。
最初はどのように手をつけたら良いのかわかりませんでしたが、解き方を身につけること意識しながら反復していました。
ここではスタディングを使った場合のお話をしましたが、書籍で勉強する場合は問題集を1冊選んで、それを集中的に繰り返すことをおすすめします。
試験対策その3:なんでこうなるのか理解する
「何でこういう答えになるんだろう」っていう疑問を抱えてはいるけど、機械的に作業を覚えてしまえば解けてしまう問題が結構あります。
でも、理屈のない暗記はすぐに頭から消えてしまいます。
答えが出るまでのストーリーが頭に入っていた方が、格段に頭に入りやすくなるし、仮に忘れてしまったとしても、ストーリーの一部が思い出せればそれをヒントに解答を導ける可能性もあるので、丸暗記するよりも断然効率がいいと思います。
「理解が大事なのはわかってる。でも、難しくて理解できないんだよ!」
と思った方も多いはず。
まさにその通りで、理解するってものすごく難しいんですよね。
建築士試験でも解答解説を読んでも意味がわからない、テキストを読んでもよくわからない、ネットで調べてもよくわからない問題は、結果どうにもならなくて丸暗記に走るってパターンでした。
でも、簿記では上でも紹介したふくしままさゆき先生の動画を見ればバッチリ理解できます。
簿記を勉強している方なら聞いたことがない人はいないくらいおなじみの動画です。
簿記のしくみ、なぜこうなるのかを丁寧に解説してくれています。
自分の場合はスタディングの講義や問題解説でおやっ??と思ったところはこの動画を見て補足しながら勉強を進めました。
試験当日の様子
実際に試験会場に行ってから試験終了までこのような感じで進みました。
自分は午前9時からの試験だったので、8時45分ごろ会場に入りましたが、すでにほとんどの人が机に座っていました。
集合時間の30分前から試験会場に入れるみたいです。
机の上に置けるものは筆記用具と消しゴム、電卓、時計、受験票、身分証明書です。
試験中に試験官が身分証明書をチェックしに来ます。
受験票と身分証明書を忘れてしまった場合も何かしら対応はしてくれような雰囲気はありましたが、
当日は忘れずに持参しましょう。
あと、携帯電話は電源を切るように指示がありました。マナーモードはダメみたいです。
午前9時から試験の注意事項について説明が始まりました。
説明が終わると問題が配られます。
そして、9時10分から試験がスタート。
10時10分に試験が終了しました。
試験終了後は解答が回収されてすぐに解散です。
問題用紙ですが、問題用紙と解答用紙と計算用紙がセットになった冊子になっています。
冊子を開くと左側に問題、右側に解答記入欄となっています。
最後のページだけが3つ折り用紙になっていて、計算用紙がくっついています。
全てが一体になっているので試験が終了するとその冊子ごと回収されてしまいますので、自宅に問題を持ち帰ることができません。
計算用紙部分だけを切り取って持ち帰るとかもできません。
試験が終わったらすぐに答え合わせをすることができないのがちょっと残念。
上でも書きましたが、試験問題は第1問→第3問→第2問の順番で解いていきました。
第1問の仕訳問題は予定通りと言った感じで進めることができましたが、次の第3問は予定よりも時間がかかってしまいました。
というのも、最終的に借方と貸方の合計が合わずにどこがおかしいのか見直しに時間がかかってしまったからです。
幸い、おかしいところが見つかって修正できたのでよかったですが、本番で計算が合わないと結構焦ります。
こういうときのためにも元になる仕訳や計算根拠等、あとで見返せるようなメモを計算用紙に残しておいた方が良いと思いました。
ただ、このメモに時間をかけすぎるのも良くないので、模擬試験を利用してどこまでメモしたらいいか練習しておいた方がよさそうです。
そんなわけで第3問で大きく時間を使ってしまい、次の第2問にかける時間が10分もなかったので、第2問で出題された2題のうち、1題をちゃんと解いてもう1題は捨てるという結果となりました。
試験成績発表
(2023年4月5日追記)
合格証と一緒に成績が届きましたので発表します。
第1問 36/45
第2問 20/20
第3問 35/35
計 91/100
一番自信があった第1問でまさかの3つ間違い。
自信のなかった第2問、第3問が満点という、全く予想していない点数となっていてビックリでした。
仕訳問題で3つも間違えていたのが悔しいですが、全体としては9割以上得点できたので良しとします。
まとめ
最後にまとめですが、試験に合格するためには簿記の仕組み・問題の解き方を理解する。
理解した上で、問題をひたすら反復演習です!
あたかも、自分で考えたやり方のように書いてきましたが、これは過去の合格者の皆さんがやってきた勉強方法です。それを真似させてもらって自分も合格することができました。
あと、合格までにどのくらい時間がかかるのかについて。
合格までにおおよそ100時間は必要だと言われています。
自分の場合は何も勉強しない日や、建築士試験の勉強をしている日もあってダラダラ勉強していたので、勉強を始めてから合格まで4~5ヶ月くらいかかってしまいましたが、まとまった時間で集中して勉強すれば数週間~1ヶ月程度の勉強期間で合格できると思います。
(現にそのくらいの勉強期間で合格する人が多いようです)
さて、次は2級です。
3級で勉強した内容を忘れないようにしたいので引き続き2級の勉強に入るつもりです。
建築士試験の勉強も始めているので、少しずつ勉強を進めていきます。