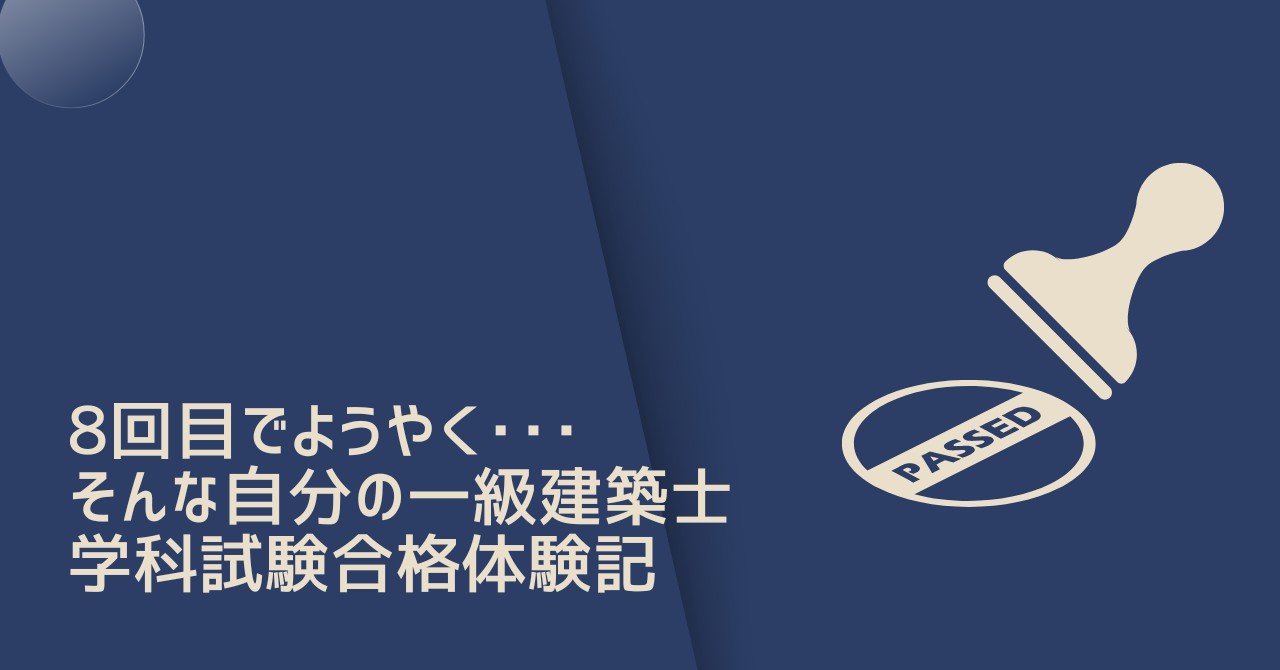スマートフォンがこの世に出てきて10年近くたったでしょうか。
この10年の間に持っていない人を探すのが難しいくらい急速に普及しました。
1級建築士を受験する世代は20代、30代、あたりが多いと思いますが、下記のデータによると、この世代は90%以上がスマートフォンを持っているようです。
| 全体 | 6~12歳 | 13~19歳 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80歳以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 39.1% | 17.9% | 64.3% | 83.7% | 72.1% | 53.9% | 33.4% | 11.0% | 3.7% | 1.6% |
| 2014 | 44.7% | 20.5% | 71.7% | 88.9% | 79.0% | 64.6% | 42.5% | 16.2% | 5.3% | 1.2% |
| 2015 | 53.1% | 31.8% | 79.3% | 92.9% | 86.2% | 74.8% | 56.9% | 28.4% | 9.2% | 1.9% |
| 2016 | 56.8% | 33.8% | 81.4% | 94.2% | 90.4% | 79.9% | 66.0% | 33.4% | 13.1% | 3.3% |
| 2017 | 60.9% | 30.3% | 79.5% | 94.5% | 91.7% | 85.5% | 72.7% | 44.6% | 18.8% | 6.1% |
スマートフォンをどのくらいの時間、何に使っているかという調査も行われているようで、この調査によれば、スマートフォンの1日の利用時間が2時間から3時間という人が最も多く、使い道としてゲームやSNS、動画配信サービスに使用している人が多いようです。
(データ出典:MMD研究所「2018年版:スマートフォン利用者実態調査」)
自分もすき間時間に無意識のうちにスマートフォンでyoutubeをチェックしたりニュースサイトを読んだりしてしまっています。
このすき間時間が積もり積もると結構長い時間になるんですよね。
この時間を建築士試験の勉強に使わないのはもったいないということで、今回は1級建築士試験にスマートフォンをどう活用するかについてまとめてみます。
教材アプリを使用する
調べてみると1級建築士試験対策用のアプリがいろいろ出ていたのにビックリしました。
その中で今回は3つ取り上げて、それぞれ特徴を箇条書きであげてみます。
各アプリについてApp StoreとGoogle Playへのリンクを張っておきました。
1級建築士絶対合格!過去試験対策問題集はGoogle Playで見つからなかったのでApp Storeのみです。
「1級建築士」受験対策
・過去13年分の問題が収録されている
・4択問題や一問一答形式だけでなく、虫食い問題や参考資料が収録されている
・問題を解くための「ヒント」が表示される
・グラフなどで成績管理をしてくれる
・問題が難易度設定されている
・有料アプリであること(980円)
・法規が収録されていない
1級建築士絶対合格!過去試験対策問題集
・問題が難易度別(レベル1~3)になっている
・5科目収録されている
・出題は選択肢1肢ごとの○×問題はなく、4択問題のみ
・間違えた問題だけ、チェックした問題だけなどの復習が可能
・レベル1の問題は無料で使えるが、レベル2と3は有料
・過去何年分の問題が入っているのか不明、その年度全ての問題が入っているかも不明
1級建築士暗記カード+過去問 解説付き
・平成25年度~平成29年度までの5年分の過去問が収録されている
・5科目収録されている
・年度別か分野別の出題形式
・出題は選択肢1肢ごとの○×問題はなく、4択問題のみ
・わかる問題わからない問題の仕分けができるようになっている
・暗記カードは5科目合わせて300語分用意されている
・完全無料
上記3つのアプリをダウンロードして見てみましたが、解説の中身や問題の出題形式を比べると「1級建築士」受験対策が有料アプリなだけあって充実している印象は受けました。
1級建築士暗記カードの暗記カード部分はすき間時間に言葉の意味を覚えているかをチェックするのに使えそうです。
これが無料で提供されているのはありがたい。
ただ、このアプリだけマスターしても学科試験に合格できるだけの知識が身につくかどうかは個人的には疑わしいと思います。
あくまでもメイン教材の補助としての使い方をするのが良いと思います。
テキストを読む
テキストや問題集をPDFファイルにしてスマートフォン入れておけば重たい書籍を持ち運ぶ必要も無く、いつでも勉強することができます。
しかし、市販のテキストや問題集は紙媒体ですので、本を裁断してスキャナで読み込みPDFデータ化する作業が必要になります。
この作業のことを「自炊」といいます。
僕はビジネス書を自炊してスマートフォンで持ち歩きたいと思って裁断機と専用のスキャナを購入して夜な夜な自炊作業をしていた時期がありましたが、これがなかなか時間もかかるし面倒な作業なのです。
でも、この自炊を代行してくれるサービスがある事を知りました。
多少お金はかかりますが、自分で裁断機やスキャナを揃えるより安いし、早くて手間がかからないのでよっぽど楽です。
「自炊代行」で検索するといろいろ情報が出てきます。
合格物語ユーザーはテキストがすでにPDFファイルになって提供されているのでそれを使うのがベストだと思います。
僕もこのテキストデータをスマートフォンに入れていますが、文字が小さくなってしまって少し読みにくいところが唯一の欠点です。
耳を使って学ぶ
最近発売されている教材は音声教材が付属されているものが増えてきました。
ほとんどの場合音声データがMP3ファイル形式で提供されます。
これをスマートフォンに取り込んでおけば、何かしながらでも勉強することができます。
また、音声で読み上げられる文章をまとめた資料も提供されているので、読み上げられた文章を見ながら音声を聞くこともできるようになっています。
このデータを2.0倍速とか速いスピードで聴くことで直前期など広い範囲を一気に復習したいときなどに役に立ちます。
しかし、これは個人的な見解ですが、聞き流す英会話学習と同じで、ある程度知識が頭に入っていないとただ音が聞こえているだけであまり意味がありません。
いきなり音声を使うのではなく、ある程度勉強した後に復習のために音声データを使うのが効果的ではないかと思います。
電車通勤の場合は通勤中にスマートフォンを見ることができますが、車通勤の場合はそれができません。
でも、運転中も耳は空いているんですよね。
このような音声データをスマートフォンで流すことで運転しながらでもラジオを聴く感覚で勉強を行うことができます。
自分は車の中にBluetoothで使用できる小型のスピーカーを置いていて、それとスマートフォンを接続して音声データを聴いています。
スマートフォンからの音だと聞きにくいので、外部スピーカーを接続することで聴きやすくしています。
スマートフォンでの勉強は移動時に限定した方が良い
スマートフォンを活用することでいつでもどこでも勉強することが可能になりました。
大変便利になったことは確かなのですが、スマートフォンでの勉強も良いことばかりではありません。
スマートフォンは多機能であるが上に勉強するためには邪魔な誘惑も多いのです。
SNSやゲーム、メールの着信、電話の着信がそれにあたるのですが、スマートフォンに着信が入るたびに集中力がそがれてしまうし、勉強に疲れてくるとSNSやゲームに気になってしまい、少しのつもりが長い時間やりこんでしまったなんて事もよくある話です。
そこで、スマートフォンを使っての勉強は、電車等での移動時や出かけている時など限定的なものにすることをおすすめしたいです。
自宅や図書館、自習室などで勉強するときはできるだけスマートフォンでの勉強は避けた方が良いし、オンライン授業を視聴するときはPCを使うか、余計なアプリが入っていないタブレットを使うことをおすすめします。
勉強効率とスマートフォンについては別の記事に詳しく書きましたのでこちらも読んでみてください。

まとめ
上記以外の使い方として、僕はXmindというマインドマップ作成ソフトを使ってノートを作っているので、このデータをスマートフォンで持ち歩いています。
XmindはPC版もスマートフォンのアプリ版も揃っていて、データも共有出来るのでマインドマップ自体はPCで作っておいて、そのデータをドロップボックスやシュガーシンクなどのクラウドサービスを使ってデータ共有して、アプリ版のXmindに取り込んでいます。
ひとつ気をつけなければいけないのは、試験当日、スマートフォンやタブレットなどの端末は1日中封筒に入れて保管しなければなりません。
休み時間もその封筒を開封して端末を使ってはいけないので休み時間に端末を使って復習することはできません。
勉強道具をスマートフォンだけにしてしまうと試験当日がちょっと不便かもしれません。
仕事をしながら勉強するのはとても大変です。すき間時間でもスマートフォンでも、使えるものは何でも使って効率よく勉強していきたいものです。